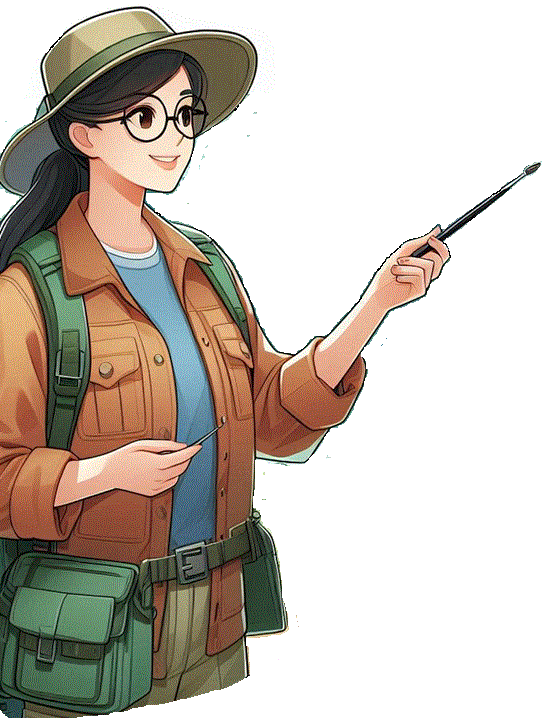Lithocarpus edulis (Makino) Nakai
・和名マテバシイの語源には諸説があり、シイより味が落ちるが「待てばシイの実のようにうまい実がなる」という意味とも言わ
れるが、はっきりしない。「待てば美味しい」 だが、最も美味しいのは、スダジイ。
・マテバシイは葉がマテガイの形に似るからと言われるが、九州や千葉県ではマテジイの名も広く、シイよりも細長い果実がマテ
ガイに類似し、葉も果実もマテガイを思わせるので付けられたと言われる。
・潮風に耐え、防風林とする。また公害にも強く、都市の緑化樹としてよく用いられる。
・学名Pasania edulis の edulis は英語の edible に相当するラテン語で、「食べられる」の意味。
・松浦市鷹島では、マテバシイを原料にした焼酎が製造されている。
・千葉ポートパークではマテバシイが多く植樹され、30年経過し防風林の役割も果たしている。
・千葉ではトウジイとも言われる。
千葉県
南房総市烏場山、鴨川市に純林が見られる。
全国
日本固有種で本州の房総半島の南端、紀伊半島、九州。
温暖な沿岸地に自生だが、ほとんど植栽されたものが多い。
- 幹は暗褐青灰色、滑らか、若枝は無毛。雌雄同株。
- 葉は互生、楕円形で全縁。厚く平滑で、光沢がある。
- 花は、黄褐色の10cm程度の雌雄花穂を結ぶ。雄花は皿状の花被から長い12本の雄蕊が突き出る。
- 雌花は三つに分かれた雌蕊がある。
- ドングリは長さ 2~3cm にもなる。沖縄まで含めるとオキナワウラジロガシが最大でその次の大きさ。
- 花の時期:5~6月頃、黄褐色の 10cm 程度の雌雄花穂を結ぶ。
- 果実の時期:開花後翌年の秋
タブノキ
常緑で葉が大きい。鋸歯がない。ドングリの形状がピストルの弾に似ている。タブの葉と似ているが、タブノキの葉柄はマテバシイよりもやや長い。葉裏の色は、マテバシイは茶色っぽいが、タブノキは白っぽい。マテバシイの葉柄の付け根は丸く膨らむが、タブノキは膨らみがない。
- 建築材・器具材。街路樹、防風樹、防火樹。
- 実はタンニンをあまり含まないため、アク抜きを必要とせず、そのまま炒って食用になる。粉状に粉砕してクッキーの生地に混ぜて「縄文時代のクッキー」として味わうこともできる。
- 代表的なクラフトの材料。
 マテバシイの樹皮
マテバシイの樹皮
 マテバシイの葉
マテバシイの葉
 マテバシイのクラフト
マテバシイのクラフト
 マテバシイのクラフト
マテバシイのクラフト
作成者:松島 学
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。