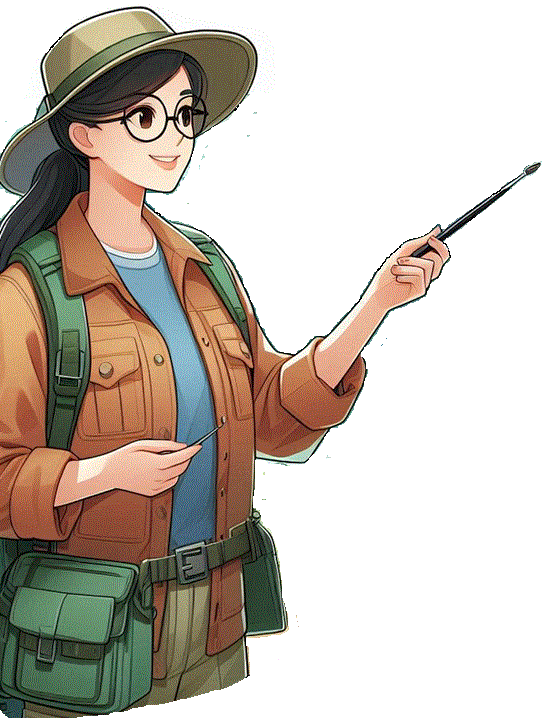千葉県のレッドデータブック上では同じ最重要保護生物でありながら、ヒメコマツは回復計画もあり、イヌブナよりも大切に扱われているようだ。ヒメとイヌとの差であろうか… (上谷)
特徴の項に記載されているとおり、氷河期の生き残りとされています。氷河期から温暖な気候への環境の変化に対応して、気温が下がる標高の高い場所に移動して房総の最上部まで登り詰め、現在の気候の中で何とか生き延びている種とされています。その為、絶滅の恐れが高い種となっています。房総の標高が低いため、それ以上は上に移動できずに生育しているヒメコマツのシ状態に対して、千葉大学教授で県立中央博物館の館長を務められた沼田真先生は「寸詰まり」と表現しています。
まだ、自然保護の考えが広がっていなかった半世紀以上前には、五葉松として盆栽用に掘り取られたことがあり、庭木用に採取されたキヨスミミツバツツジと同様に数が大きく減少しました。その後、地元の自然を守らなければと立ち上がった人達が県立中雄博物館などと協力して保護に尽力しています。ただ、地球温暖化が進む中、更なる危機が迫っていると心配されています。(竹内)
千葉県
分布がごく限られているか、生育が極めて少ない。高宕山系、元清澄山系、清澄山系の一部。
全国
関東以西の本州、四国、九州北部。
山地性で、急峻な崖に自生する。
- 幹は高さ30m、直径100㎝に達する常緑針葉高木。多くは標高1000m付近に生育するが、房総の 400mに満たない低山で生息しており、千葉県に小氷期があったことを示す遺存的な種であると考えられている。
- 樹皮は若い時季には緑がかった灰色、のちに暗灰色となり、薄い鱗片となってはがれる。枝を水平に出す。
- 針状葉の断面は三角形で短枝上に5本束生する。雌雄同株で単性花。5~6月新枝下部に雄花、新枝先端に雌花をつけ、球果が熟すのに2年かかる。
- 湿地や潮風、大気汚染には弱いが、乾燥には強い。
- 1970 年代から、房総丘陵の生育数が急減した。マツ材線虫病や、干害、稚樹の山取りなどの諸影響が考えられるものの、詳細については不明のものも多い。個体の消失に対して千葉県内では「ヒメコマツ回復計画」が策定されている。
キタゴヨウマツ
・球果が キタゴヨウマツに比べ小型で丸い。熟しても裂開しない。種子の翼が短く、薄くてもろい。 キタゴヨウマツは球果が大型
で長い。熟すと裂開する。種子の翼が長く硬い。
・葉の長さが キタゴヨウマツよりも短い。
・キタゴヨウマツは福島県以北に自生し、千葉県では自生していない。
- 全国的に盆栽として人気が高い。現在でも多くの固体が園芸用に栽培されている。
- 建築用としては一部利用されるものの、割れやすく耐朽性も弱いため、アカマツのように梁などには使用されない。
- 木目が通直で、肌目も均質、緻密で狂いも少ないことから、ピアノの鍵盤下地やバイオリンなどの弦楽器の腹板に柾目材が使われる。
- 材が軽軟で切削加工性がよいため、鋳物工業の木型材として、自動車や機械などの模型製作にも利用されてきた。
 山の頂上に生息する残り少ないヒロコマツ(清澄山系)
山の頂上に生息する残り少ないヒロコマツ(清澄山系)
作成者:上谷 修一郎 (竹内追記)
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。