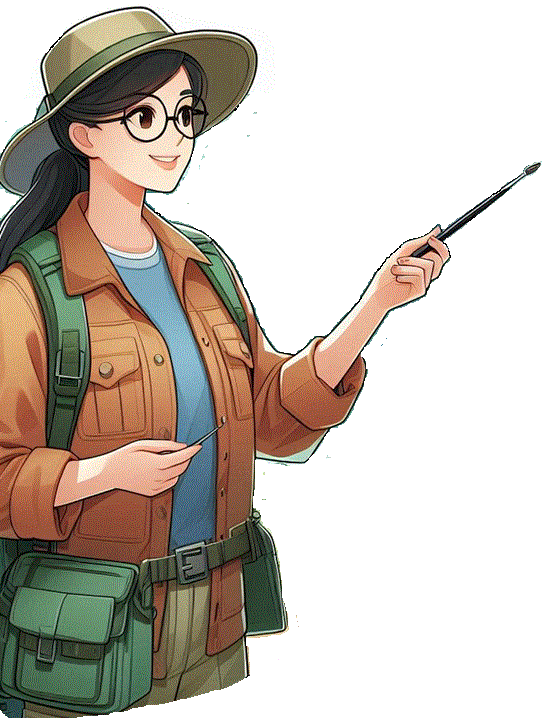冬でも緑の葉をつけるサカキやヒサカキは生命力の象徴として宗教的な利用が多い。サカキが手に入らない関東地方以北ではより耐寒性のあるヒサカキが神社や神棚に供えられる。本種は名前も本来のサカキでないから非榊であるとか、一回り小さいので姫榊がなまったとかの説がある。西日本では神事にはサカキ、墓・仏壇へのお供え(仏さん柴)としてはヒサカキ、と使い分けるところもある。
サカキと混同されやすいので、サカキは「ホンサカキ」、「マサカキ」と呼ばれ、ヒサカキは「シャシャキ 」、「シャカキ」、「ビシャコ」、「ビシャ」、「ヘンダラ」などとさまざまな地方名で呼ばれる。
春に咲く花には独特の強い匂いがあり、ガス漏れと勘違いされる事例もある。
参考:「樹に咲く花」山と渓谷社、「樹木の見分けポイント図鑑」講談社、ウイキペディア
千葉県
県内全域に分布し、よく見られる。
全国
本州(青森を除く)、四国、九州、沖縄。
山地の林内にごく普通にみられる。日本の木で最も個体数が多いという推計もある。
- 常緑の低木~小高木で、大きいものは高さ10mほどになる。
- 本年枝は緑色。樹皮は暗褐色~黒灰色。
- 葉は互生し、葉身は3~7㎝、幅1.5~3㎝の楕円形で先が尖り、先端がわずかに窪む。光沢がある厚みのある革質で、浅い鋸歯がある。両面とも無毛。葉柄は2~4mm。
- 花は雌花、雄花があり雌雄異株だが、まれに両性花もある。花期は 3~4 月、葉腋に鐘型、つぼ型の花を 1~3 個束生する。花は下向きに咲き、強い臭気がある。花弁は帯黄白色。
- 果実は10~11月に紫黒色で液果をつけ、約5㎜の球形で鳥が好む。
サカキ、ハマヒサカキ、ヒメヒサカキ
葉に鋸歯がある(ヒサカキ)かない(サカキ)か。花は、ヒサカキは雌雄別株、3~4 月に鐘型、つぼ型の強い臭気の花。サカキは6~7月、白色のちに黄色の花。
ハマヒサカキは雌雄別株。花期は 11~12 月頃。淡黄緑色の花、臭気あり。葉は縁にうすい鋸歯があり、先は丸く基部はくさび型で裏面に少し巻き込む。海岸林に普通な小高木。
ヒメヒサカキ は屋久島の固有種。
- 枝葉をサカキの代用品として神事に使う。心材、辺材ともに淡褐色で、床柱や器具材に利用。また薪炭材にもする。木灰は和紙の製造に、果実は染料に使用する。
 ヒサカキの花(坂本)
ヒサカキの花(坂本)
 ヒサカキの果実(米澤)
ヒサカキの果実(米澤)
作成者:米澤 理雄 (2024.11.1一部改訂 坂本 玲子)
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。