NPO法人千葉県森林インストラクター会
種 名
漢字名
花筏
別 名
英 名
学 名
樹木区分
落葉低木
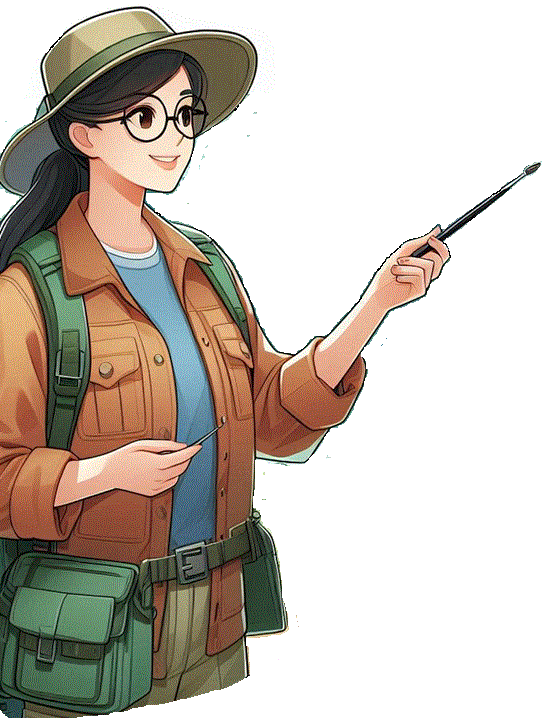
森林インストラクターの一口メモ
別名のヨメノナミダは、昔殿様の使いから「葉に実のなる木を見つけてくるように」と命じられた若嫁が、夜遅くまで山中を探したが見つからないため、思わず流した涙が葉の上に落ち、月光に黒真珠のように輝いたものが、ハナイカダの果実になったという説話に由来するといわれている。
当会会員のHさんの解説での物語、「昔、神様が植物を集めて、葉はどこに、花はどこに付けるかなどをお話をされていた時に、ハナイカダはおしゃべりをしてい聞いていなかったため、いざ花を咲かせてみたら、皆と違う変な形になってしまった。」はこのシシ樹木の特徴をよく表しています。この話を解説の冒頭にすると、参加者が話を聞いてくれるのに効果があるとか。(上谷、竹内)
<分布状況>
( 千葉県レッドデータブック ― )
千葉県
県内に広く分布する。
全国
北海道南部~九州。
<生息地・生息環境>
低山地の林内や湿気のある沢筋。
<特 徴>
- 株立ち樹形。
- 葉は互生し、10㎝前後の卵形で、先端は尾状に長く伸び、鋸歯がある。
- 葉柄と葉軸の中間まで花柄が合生しているため、葉の中心に花が咲く。この形から、ハナイカダの名がある。
- 花までの葉の主脈は太く、表面にやや突起しているが、花より先では主脈、側脈とも細くなり、やや凹んでいる。
- 花期は5月頃。径4~5mmで淡い緑色。雌雄異株で、雄花は10個前後、雌花は1個、時に2~3個が1枚の花の上に咲く。
- 花が咲いていないときの葉の特徴は、①両面無毛で、光沢がある②鋸歯が糸状に尖っている③中央付近に花や実がついた跡があること。
- 花の後に、雌株では径7mmほどの球形の果実が実り、黒く熟す。
<類似種・一緒に覚えたい樹木>
コバノハナイカダ
<見分け方>
コバノハナイカダは葉が小形で長さが3~7㎝、側脈が2~4対。
<利 用>
- 新芽が柔らかいため、菜飯や汁の実、おひたし、天ぷらなど食用として利用。


作成者:上谷 修一郎 (竹内)
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。