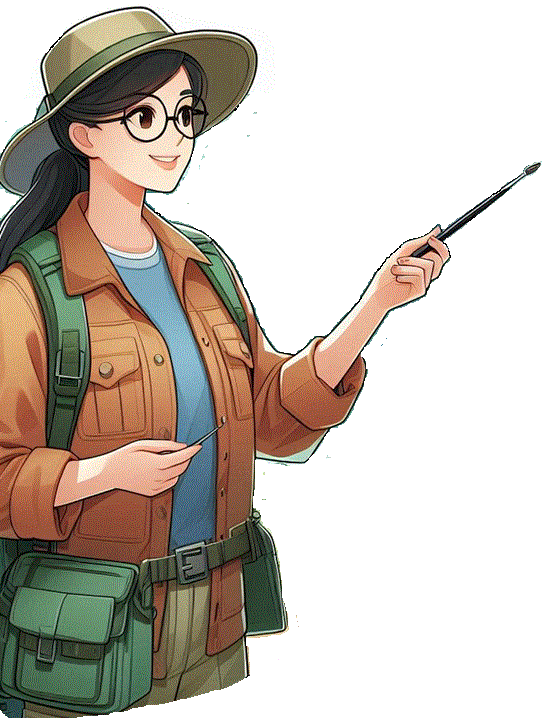花粉症のために、厄介者の憂き目にあっているが、放置されたスギ林を整備することで活力を取り戻すことが大切である。秋田県の旧二ツ井町の天然スギ保護林は、平均樹齢250年の天然スギ3千本が林立していた。見事な美林として後世まで残したい景観であった。(富永)
下記のとおり「サンブスギ”」は有名ですが、基本的にサンブスギは切り取った枝を培地(培養する場所)となる所に挿して発根(根を出させる)させる挿し木という手法で苗木を育てています。動物などではなかなか考えられない現象ですが、植物では枝や葉などの器官から根などの器官が育つことがあり、この性質を利用した方法です。この方法だと単一生殖なので、遺伝形質が元の親木と変わらず、分身(クローンといいます)のようになります。このため、サンブスギは遺伝形質が同じのため、病原菌などに一斉に感染してしまうという弱点を持っています。そして、サンブスギには「スギ非赤枯性溝腐病」という長い名前(短く溝腐病と呼ぶことも多いです)の病気が蔓延してしまいました。これに感染すると枯れはしないのですが、幹に溝状に腐った個所が出来てしまい、建築用材として使い物にならなくなってしまいます。また、幹に腐った溝があるので強度が弱くなり風折れしやすくなります。(竹内)
千葉県
全域に見られる。中でも山武地域では江戸時代からの平地林業が行われ、「サンブスギ”」ブランドとして有名。
全国
北は西津軽郡鯵ヶ沢国有林、本州、四国、九州、南は屋久島まで。断続的に冷温帯から暖温帯に及んでいる固有種である。
「谷スギ、尾根マツ、中ヒノキ」と言われるように、土地が肥沃で地下水位が高い所で生息する。静岡・高知・鹿児島など太平洋側に分布するスギを「オモテスギ」と呼び、秋田・新潟・山陰など日本海側の雪国に分布するスギを「ウラスギ」と呼ぶ。天然のオモテスギは実生による天然更新、天然のウラスギは伏条更新が特徴である。
- 大きいものでは樹高50mほどになる常緑高木。幹は通直し、樹冠は楕円状円錐形で、老木になると丸くなる。 葉は小型の鎌のような針形で、らせん状に並ぶ。
- 同じ個体に雄花と雌花をつける雌雄異花。春にはスギ花粉を大量に飛ばし、社会問題化している。
- 赤と白色で、心材と辺材の区別が明瞭。肌はやや粗く、木目は真直ぐで通りが良い。
- 杉の葉は、日照で赤くなるものがあり、日陰の緑との違いが際立つ。
オモテスギとウラスギ
オモテスギに比べて、ウラスギのほうが葉の開く角度が狭いものが多い。
- 「スギ文化」と言う言葉があるほど、日本人にとっては身近な樹種である。建築材、家具材、線香、器具材はじめ、身の回りに見られるほとんどの製品、用品に使用される。また発酵食品の樽等にも適している。
 スギ賀茂神社 650年大杉
スギ賀茂神社 650年大杉
 サンブスギ森
サンブスギ森
 スギの雄花
スギの雄花
 スギの雌花生息地・生息環境
スギの雌花生息地・生息環境
作成者:富永 好郎 (竹内追記)
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。