NPO法人千葉県森林インストラクター会
種 名
漢字名
白樫、白橿
別 名
英 名
Japanese white oak
学 名
樹木区分
常緑高木
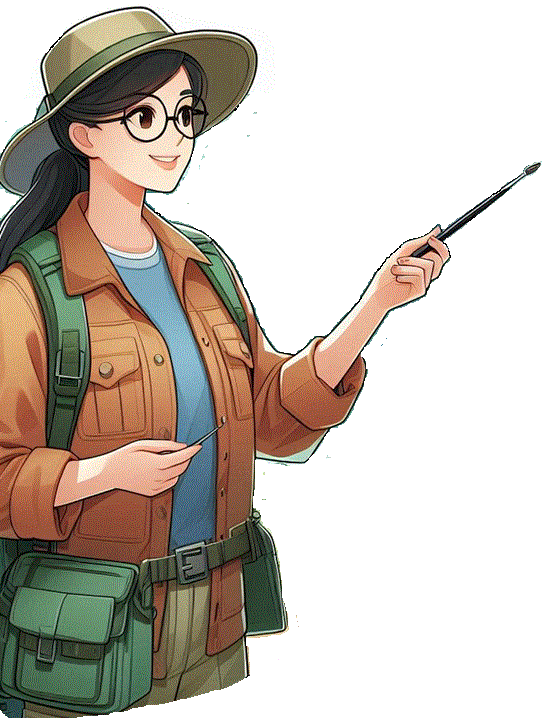
森林インストラクターの一口メモ
学名の myrsinaefolia は、シラカシの葉がギンバイカに似ていることに由来する。
またシラカシはカシの名の由来とされる「堅し」のとおり、かたく粘りもあるため、成木の中にはなかなか伐採できない木もあるらしい。その場合、林家は時間をかけて徐々に枯らしていく作戦をとることもあるようだ。
<分布状況>
( 千葉県レッドデータブック ― )
千葉県
広く分布し、生育が普通に見られる。北部中部に多く、南部には比較的少ないとされる。
全国
福島県、新潟県以南の本州、四国、九州。朝鮮半島および中国。
<生息地・生息環境>
暖地の山野に自生する。
<特 徴>
- 幹は高さ20m、直径60~80㎝に達する。
- 若木の樹皮は灰褐色でカシ類では比較的白いが、成木では黒褐色になり、カシ類では最も黒くなる。
- 葉身は長さ7~14㎝で細長く、長さ1~2㎝の葉柄があり、葉の上半部に低く鋭い鋸歯がある。
- 雌雄同株で、4~5 月頃に新葉とともに開花し、多数の雄花をつけて下垂する。毎年実がなり、8 月頃より急速に大きくなる。球果は秋に熟し、柱頭の基部が膨らみ、殻斗は灰色。
- シラカシは寒さに強い(カシ類の中で最も耐寒性があるといわれる)ので特に関東によく見られ、西のアラカシに対して東のシラカシと言われる。
- 材がアカガシに比べ白いことが名前の由来といわれる。
<類似種・一緒に覚えたい樹木>
アカガシ、ウラジロガシ
<見分け方>
シラカシの葉の裏は淡い緑色。上半部に粗い鋸歯がある。アカガシの葉の裏面は灰白色で伏せ毛が密生。通常は全縁で、鋸歯がなく、葉の先端部分がうねる程度。また葉柄が長い(また同じコナラ属で葉柄が短いのはツクバネガシ)。
ウラジロガシはカシ類では最も標高の高い所まで生育する。葉身は長さ 7~11 ㎝の被針形で、先端から 2/3に低く鋭い鋸歯が疎らにあり、葉先が鋭い。学名をQ. Salicina Blumeといい、salicinaが「ヤナギのような」という意味なので、葉の形からきたものと考えられている。葉が波打っているおり、葉の裏が蝋分を分泌して名前のとおり、白さが目立つ。
<利 用>
- 材は粘りがあり、良質であるとされ、薪や炭、器具や建築、楽器などに利用された。また生垣や庭園、公園などによく植栽される。



作成者:上谷 修一郎
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。