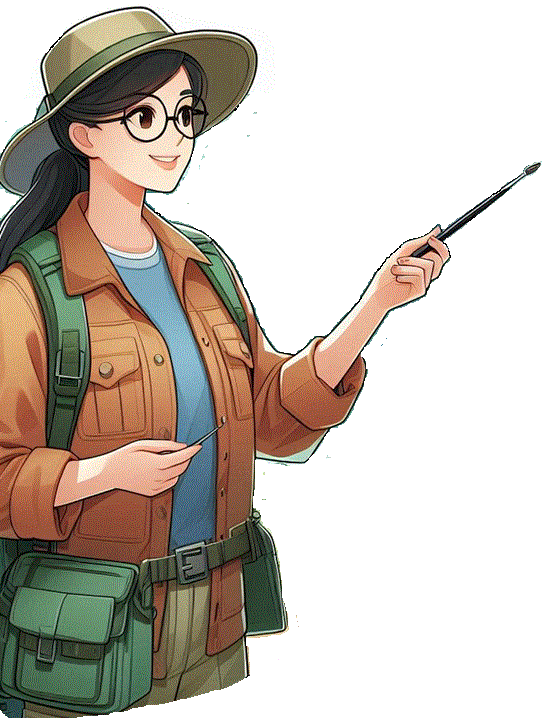花や葉、実、さらに根から茎にいたるまでの全てが毒成分を含む。特に、種子にアニサチンなどの有毒物質を含み、食用すると死亡する可能性がある。シキミの実は植物としては唯一、毒物及び劇物取締法により劇物に指定されている。香辛料や漢方薬として利用される同属のトウシキミの実(八角)と似ているため、誤って食べて死亡した事例があるという。
一方で、精油を含んだ葉や樹皮は芳香を持ち、寺院や墓地に多く植えられる。仏前に供え、抹香の原料とすることや、土葬時に死臭や動物の侵入を防ぐ効果が期待されたものであろう。さわったり飾ったりすることでは毒にあたる心配は無い。
シキミの語源は、四季を通して美しいことから「しきみ しきび」となったと言う説、また有毒なので「悪しき実」からともいわれる。
千葉県
全域に分布。
全国
東北南部以南の本州、四国、九州、沖縄。
山地に生える。寺社や墓地にもよく植えられている。
- 樹高2~5m。
- 花は両性花で、花期は 3~4 月。花弁は淡黄白色の披針形で 10~20 枚がややねじれたように葉の付け根から1つずつ出て咲く。花径は3cm。
- 果実は袋果が星形状に並ぶ八角形で、8本の突起が出ている。9~10月に上面が裂開し褐色の扁平な種子が出る。
- 葉は長さ4~10cmの倒卵形で枝先に集まってつく。光沢があり、葉脈はほとんど見えない。ちぎると抹香の香りがするが毒があるので注意。花にも香りがある。
- 樹皮は暗灰褐色、初めは平滑だが、老木になると浅く縦裂する。
ミヤマシキミ、ツルシキミ
三種は葉の形やつき方が似る。ミヤマシキミ、ツルシキミはミカン科ミヤマシキミ属。ミカン科なので、葉をちぎると柑橘類の香りがする。シキミの花は10~20弁で径は3cmほどだが、ミヤマシキミ、ツルシキミは直径約1cm。花弁は4個である。また樹高は、ツルシキミで0.5m、ミヤマシキミは1~1.5mほどである。ツルシキミは日本海側の多雪地帯の林床に自生する。
- 空海が青蓮華の代用として密教の修法に使った。青蓮花は天竺の無熱池にあるとされ、その花に似ているので仏前の供養用に使われた。
- 葬儀には枕花として一本だけ供え、末期の水を供ずる時は一葉だけ使う。納棺に葉などを敷き臭気を消すために用いる。関西では、お祝いや葬儀の際の表に飾る花輪の代わりにシキミをお供えとして使用する。
- 葉を乾燥させ粉末にして末香・線香・丸香としても使用する。樒の香気は、豹狼等がこれを忌むので、墓前に挿して獣が墓を暴くのを防ぐらしい。樒には毒気があるがその香気で悪しきを浄める力があるとする。
 シキミの花
シキミの花
 シキミの果実
シキミの果実
 乾燥した果実と種子
乾燥した果実と種子
作成者:鍛冶 健二郎 (2024.11.1一部改訂・写真 坂本玲子)
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。