NPO法人千葉県森林インストラクター会
種 名
漢字名
拳(辛夷)
別 名
英 名
学 名
樹木区分
落葉高木
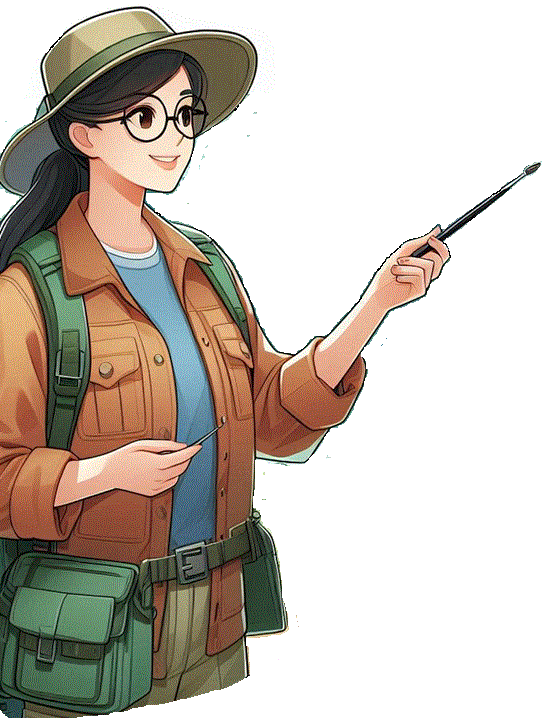
森林インストラクターの一口メモ
「こぶし咲くあの丘 北国のああ北国の春」と歌われた千昌夫さんのヒット曲で、コブシは北国の樹木と思っている方も多いかもしれませんが、植栽木も含めて温暖な千葉県にも沢山生育しています。ほぼ同時期に咲くサクラと並んで春の代表的な花です。どちらも葉が茂る前に開花するため目立つことも好まれる理由かと思います。
・コブシを歌った唄 … 『北国の春』
・アイドルグループ … コブシファクトリー
・コブシの花の各地の言い伝え
『コブシの花が咲いたら、麻まけ』 (長野)
『コブシの花が咲くとイワシがとれる』 (佐渡)
『コブシの花が咲くようになれば味噌しこむ』 (京都船井郡) 『コブシの花が咲いたら種芋をおこす』
(栃木)
『コブシの花が咲くと、サツマイモを植える』 (鹿児島)
『コブシの花が横向きに咲く年は大風多し』 コブシの花は大きいため、風に揺られやすく、どうしても
風の強い日が多いと花が横を向いてしまう事から生まれた諺。『コブシの花がたくさん咲くと、その年
は豊作』『コブシの花が下向きに咲くと、その年は凶作』
・コブシの花を扱った文学 宮沢賢治 『マグノリアの木』 堀孝雄 『コブシの花』
・ウィーン一番の目抜き通りケルントナー通りでは、街路樹として植えられている。
・山口県にある朝田墳墓群から出土したコブシの種が 2000 年の時をこえて発芽した。
ふつう、コブシの花は6枚の花弁を持つが、その古代コブシは、花によって7枚の花弁や8枚の花弁を持って
いるそうである。 (永井)
<分布状況>
( 千葉県レッドデータブック ― )
千葉県
県北部を中心に分布。
全国
北海道~九州。
<生息地・生息環境>
里山から低山に多く生え、類樹種タムシバに比べどちらかと言うと湿った平坦地を好む。
病害虫にも強く、街路樹、公園樹、庭木などに良く利用されている。
<特 徴>
- 日本、朝鮮半島南部に分布。成長すると 15m ほどの高さにもなる落葉広葉高木。葉は長さ 6cm~
- 15cm. 葉先の方で幅が最大になる倒卵形で葉先が突き出て、ふちが波打つ。全縁で互生。
- 開花時期は、 3月下旬~5月。早春を代表する花のひとつで、葉に先立ち大きな白い花を咲かせる。内側に 6 弁の花皮弁。外側に緑色の目立たない 3枚のがく弁。花の下に一枚の若葉を伴うのが特徴。
- 中央に多数の雄しべと雌しべがあり,すべてらせん状に配列されている。
- モクレン科は白亜紀の化石としても残っている地球上最古の花木とされ、コブシは日本でも鮮新世
- (約500万~200万年前)や更新世(約200 万~1万1700 年前)の地層から化石が出土している。
- 花は雌性期と雄性期があり、雌性先熟で柱頭が花柱から開出しているときが雌性期、柱頭が花柱にへばりつく様になると雄性期になり雄しべから花粉が出る。初期の虫媒花は蜜を出さず匂いで虫を呼び花粉を報酬としていたが、今もモクレン科の花はほとんど蜜を出していない。
- 花の中心の沢山の雌しべは、実ると集合果になり、10 月に裂け赤い種子が現れ垂れ下がる。鳥散布。
- 種子本体はハート型で黒く硬く、1000 年以上たっても芽を出す事が可能である。
- 漢字名の拳は、秋に実るゴツゴツした果実が幼児の拳の様に見えることから。「辛夷」という漢字を当てる事があるが、中国ではこの言葉は木蓮を指す。また日本薬局方に記載される生薬で「和辛夷」と記されるが、そのほとんどがコブシではなく、タムシバの蕾である。
- 東北地方では、桜よりも早く大きな花を咲かせるため、古くから農耕と密接な関係があり、田打桜、種蒔桜、田植桜と呼ばれて来た。また、その開花時期から日本各地で農作業のタイミングを判断したり、花の向きから豊作になるか否かを占ったりしていた。
- 葉に先立って咲かせる花は一斉に開き、満開になると、遠目には真っ白になる。壇の浦で敗れた平家の落人が熊本の山奥に逃げ隠れた時、翌朝突然山々が真っ白になったので源氏の白旗に囲まれたと思い込み自害したという言い伝えもある。
- ただ、まだ寒い時期に開花するため、寒風や霜にやられて、時には一晩でその美しい姿を変えてしまう事もある。
- 良い香りが花、枝、葉にあり、落ちた枝でもほのかに薫る。花の蕾は入浴剤としてもリラックス効果があるが、精油は抽出されていない。冬を越すために毛に覆われた冬芽を付け休眠し、春になるとその冬芽を割って一斉につぼみが出てくる。
<類似種・一緒に覚えたい樹木>
シデコブシ、ハクモクレン、タムシバ
<見分け方>
・シデコブシ
東海丘陵要素の日本固有種 準絶滅危惧(NT) 花弁と雄しべの一部が同色。
合わせて 10 枚~18 枚の花弁に見える。花びらは細長い。木の大きさ 4m~5mと小ぶり。
・ハクモクレンモクレンは中国が原産で平安時代に輸入され栽培されたもの。
花は上の方へ向き厚くふくよかな形で、半開き。花弁9枚。コブシより若干開花が早い。
・タムシバ日本固有種。別名ニオイコブシ。本州以南の日本海側に多く見られる落葉小高木。
丘陵帯~山地帯の急斜面や尾根筋。葉や枝を切るとレモンやライムに似た香りがあり、精油も抽出されるが
採集が困難を極めるため、希少価値が高い(5ml ¥10,000-ぐらい)。
噛む柴(カムシバ)が訛ったもので、 昔からその葉を噛んで元気になっていたと言われる。
日本薬局方に記載される生薬の「和辛夷(わしんい)」で、 耳鼻咽喉の漢方として有名。
コブシは花の下に葉(托葉)があるがタムシバにはない。がく弁はコブシは緑だがタムシバは白。
葉幅は狭く葉の先端はとがり、卵状長楕円形。裏面が白っぽい。
<利 用>
- 漢方 花蕾を干したものを生薬で『和辛夷』といい、蓄膿症、頭痛鎮痛薬として利用されるが、主に 日本産辛夷の大部分はタムシバ(冬芽を乾燥させたもの)を利用している。
- 木材 材質はホオノ によく似ているが、少し硬い。ホオノ 同様玩具、漆器素材などにされる。同属の花木のモクレンやハクモクレンの接木の台木とされる。皮付きの小丸太が茶室の床柱などに利用される。




作成者:永井 智津子 (竹内)
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。