NPO法人千葉県森林インストラクター会
種 名
漢字名
黒松
別 名
英 名
Japanese black pine
学 名
樹木区分
常緑高木
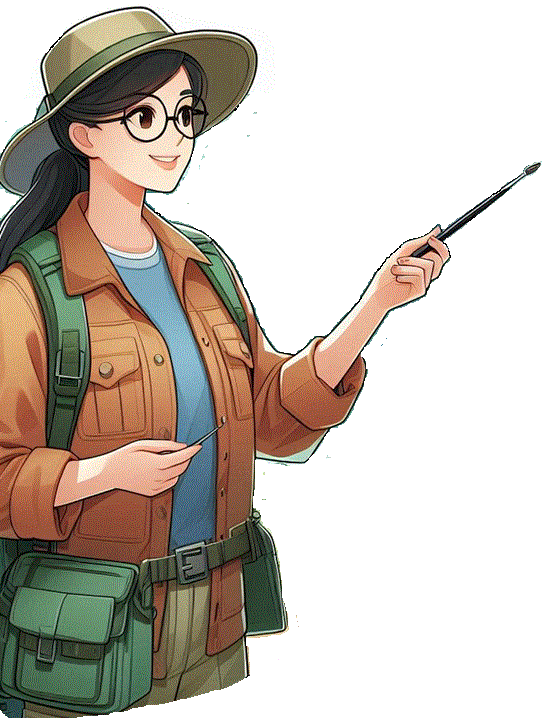
森林インストラクターの一口メモ
日本のマツが大きな被害にあったことは、よくご存じの方も多いと思うが、森林インストラクターの一人として、以下にマツノザイセンチュウとマツの被害について触れておきたい。
=センチュウとカミ リの連合軍による被害=
・病原体の正体線虫(センチュウ)はその名の通り、線状か円筒形のかたちをしている。からだのつくりは単純で、口と肛門の間
は一本の消化管でつながっている。マツノザイセンチュウ(以下、「センチュウ」)の大きさはわずか1mm程度にすぎない。
その小さなセンチュウが大きなマツを枯らす病原体。
・センチュウの侵入 センチュウは乾燥に弱く、移動能力もないので、自分で他のマツに移動することができない。それを助ける
仲立ち(媒介者)がマツノマダラカミキリという小さなカミキリムシ。5~7 月頃、マツの中で成虫になったカミキリが現れ、
健全なマツへと飛んでいく。たどり着いたカミ リは若い枝を食べ、マツからマツヤニが滲出する。カミキリの体には多数のセン
チュウがついているが、このセンチュウがマツヤニへと移動。マツヤニを伝わり、マツの中へ浸入する。害虫や菌の浸入を防ぐ役
割をもつはずのマツヤニが、センチュウにとって格好の生活場所、侵入口となっている。
・センチュウの増殖とマツの枯死マツの中に入り込んだセンチュウは樹脂道で増殖し、終にはマツを枯死させる。クロマツは、
近年、マツノザイセンチュウ病のため、全滅に近い被害を受け、林相が一変した地域も多い。
・枯死したマツとセンチュウ枯れしたばかりのマツは匂いを発するので、カミキリの雄と雌が集まり、交尾する。雌はマツの幹や
枝に溝を掘って卵を産みつける。卵からかえった幼虫は、マツの樹皮の下に滑り込み、樹皮を食べて成長するが、このころ、
センチュウがカミ リのまわりに集まってくる。カミキリは枯れたマツの中で幼虫のまま越冬し、翌年春に蛹(さなぎ)となり、
5~7 月頃に孵化して成虫になる。カミキリに集まったセンチュウは、カミ リの気管に潜入する。1匹のカミ リに平均数千~1万
のセンチュウが保持される。(植沢)
下記の生息地・生息環境の項に記載されているとおり、海岸線近くで潮風が当たり、痩せている土地でも育つ樹木です。このため、説明の時に勢い余って「クロマツは痩せ地を好む」と言ってしまうことがありますが、そのようなことは無いようです。実際に植えて育ててみると、当然ながら環境の良い場所の方が育ちが良いようです。なので、「クロマツは痩せ地でも育つ」くらいの表現が適しているかと思います。
上記のとおり日本全体で猛威をふるったマツノザイセンチュウ病のためにかつての白砂青松の景観を作っていたクロマツ林は大きな被害を受けました。千葉県でも現在は高波や潮風から農地や人家などを守るための海岸防災林として植林されて育てられているクロマツ林がほとんどになりました。特に、海岸線近くでは、広葉樹なども試験的に植林されましたが、やはり、潮風が当たる場所ではクロマツ以外の樹種が育つのは難しいようです。(竹内)
<分布状況>
( 千葉県レッドデータブック ― )
千葉県
県内に広く植林され、生育も普通に見られる。
全国
本州、九州、四国の海岸沿いに広く自生する。青森県が生育北限。関東の栃木県および群馬県には天然分布が見られない。
<生息地・生息環境>
クロマツは、陽樹で、幼樹のころから十分な陽光を要しする。土壌は肥沃でなくても、水はけの良い所に生育する。特に日当たりのよい海岸の 浜に生育し、海岸風景の主木をなす。潮風に強く古くから海岸地域の防林として植えられてきたため、白砂青松といわれる海岸林はクロマツである。
静岡県静岡市清水区(旧清水市)の三保の松原、福井県敦賀市の気比の松原、佐賀県唐津市の虹ノ松原の3ヵ所は日本三大松原に数えられている。
<特 徴>
- 常緑高木で、大きなものは樹高30~40m、直径50~80㎝に達する。アカマツよりも大木が多く、名木として天然記念物に指定されているものも多い。
- 樹皮は暗黒色または灰黒色、厚く亀甲状に割れ目ができ、やや厚い鱗片となって剥げる。
- 若いうちは円錐形、老木になると樹冠が広がり、枝は太く傘状になる。日照、風向、土壌などの環境条件に応じて幹が曲がり、それぞれ独特の形態を示す。
- 葉は光沢のない濃緑色で剛直。先端が尖り、にぎると痛い。アカマツに比べて葉が雄々しい。
- 4~5月に開花。雌雄同株。雄花は当年に伸びた枝の下部に多数群がってつき、黄色の大量の花粉をだす。雌花は紫紅色で、新枝の先端に 1~3個つく。
- 球果は卵状円錐形で、淡褐色。種子は、種子の3倍ぐらいの翼があり、10月頃成熟すると種鱗が開いて種子を風散。球果は翌年の10 月頃に成熟する。毎年若干ずつ結実し、1 年おきに豊作。
<類似種・一緒に覚えたい樹木>
マツ属には、二葉松のアカマツ、クロマツ、リュウ ュウマツ、五葉松のヒメコマツ、チョウセンゴヨウマツ、ハイマツ、アマミゴウヨウマツがある。
<見分け方>
・クロマツとアカマツを比較すると、非常によく似ているが、アカマツは葉がやや細く柔らかく、手で触れてもクロマツほど痛く
ない。そのためクロマツが「雄松」と呼ばれることに対比して、「雌松」と呼ばれることもある。
・アカマツが成長すると樹皮が鱗状に剥がれるのはクロマツと同じだが、アカマツではこれがより薄く、赤っぽくなる。
・冬芽が赤く、葉は短いのがアカマツ、冬芽が白く、葉は長いのがクロマツ。
<利 用>
- 材は粘りが強く、アカマツよりも樹脂分が多い。建築の構造材に利用するほか、光沢が出るので、内装材や廊下にも使われる。また水にも強いので、土木用坑木、枕木に橋にも用いられる。
- 庭木、盆栽に賞用される。各地の名園には必ず植栽されている。
- 塩分に耐えるので、海岸防風林、風潮林として植栽される。海岸 防および山地 防(荒廃地造林)ではもっぱらクロマツを使っている。
- マツの幹に傷をつけると滲出してくる樹液(生マツヤニ)が得られる。マツヤニから揮発性のテレピン油と非揮発性固体のロジンが精製される。テレピン油はペイント用溶剤、樹脂、合成香料原料、殺虫剤などに利用されている。ロジンは紙サイズ剤(紙にインクが滲まないための薬品)、合成ゴム、印刷用インク、塗料、接着剤などに利用されている。身近なところでは、野球のピッチャーの滑り止め(ロジンバック)。摩擦で音を大きくするために、ヴァイオリンの弓にもつけられている。



作成者:植沢 俊 (竹内追記)
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。