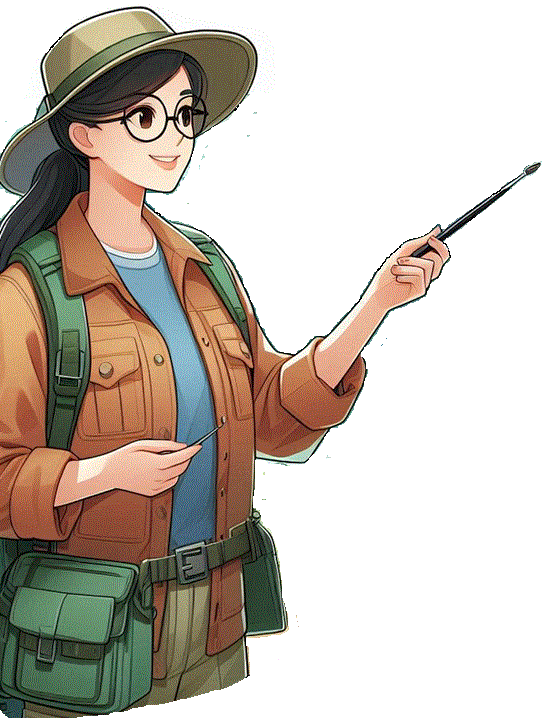チシャノキ 、ヤマヂサ、コハゼノキ 、ロクロギ (轆轤木)
Styrax japonica Sieb. et Zucc
初夏に数多くの下向きの白い花を枝にぶら下げるようにつける。花期に枝を下から見るのが美しく、庭木にも用いられる。また、球形の実の形が乳に似ているからチシャノキ と呼ばれていたようである。エゴノキ の名前由来は果皮がえごい(えぐい)から付けられたと言われ、若い実を口に入れると口の中がしびれてしまうようである。実にエゴサポニンという毒が含まれ、昔は「毒流し漁」(現在は環境への影響で多くの国で法律禁止)と呼ばれ、実の汁を川に流ししびれた魚が浮いてその魚を取ったという。一方、茶色の種はヤマガラの大好物で、他の鳥は食べないので独り占め状態となる。また、若い実をつぶし、水をかけると泡立ち、石鹸代わりにもなる。冬芽に「エゴの猫足」という虫こぶをつけることがある。 (米澤、西村)
千葉県
県内全域に普通に見られる。
全国
北海道~沖縄まで全国に分布。
関東ではコナラやクヌギとともに雑木林を代表する樹木の一つ。沿岸~山地の明るい林内、谷合、林縁などに普通に見られる。
- 高さ 10mほどにもなる落葉高木。若木の幹は滑らかで、紫がかった黒が特徴的。老木になると、灰黒色で縦に細かく割れる。
- 細い枝は節毎にジグザグに曲がっていて、折れやすい。
- 冬芽は裸芽で、大きな芽のわきに小さな副芽がある。
- 葉は互生。通常の樹木と異なり、幼木の葉は長さ 1~2 ㎝と小さく、成長するにつれ大きくなり、大きいものでは8㎝程度にもなる。
- 若い葉の裏側や、新枝には淡褐色の星状毛が目立つ。
- 花期は5~6月。白い花がたわわに咲く。花冠は径2~3㎝。純白で5裂し、中心部に集まる10本の雄しべが鮮明な黄色。ツバキ と同じように、花ごと樹下に落下する。
- 長さ1㎝ほどの果実が8~9月に熟す。実の味がえぐいことから、エゴノキ の名があるとされるが、ヤマガラの好物でもある。
- エゴノキ の枝には薄緑色のハスの花のようなものが多数つくことがあるが、これはエゴノネコアシフシといい、エゴノネコアシアブラムシによるもので新芽を食べることで刺激され変形し虫こぶになるそうです。
ハクウンボク
葉が円形で直径15cm前後あり大きく、花や実が総状花序に連なってつく点が異なる。
- 果皮にサポニンを含み泡立ちがよいため、洗剤として利用されていた。またサポニンは魚毒性もあるため、川に流して魚を捕るのにも利用されていた。
- ・粘り気があるので器具、特に和傘の轆轤(傘の骨の基点)として重宝された。別名のロクロギの由来でもある。
 エゴノキの花とハナバチ
エゴノキの花とハナバチ
 エゴノキの実
エゴノキの実
 エゴノキの冬芽
エゴノキの冬芽
 エゴノキの虫こぶ
エゴノキの虫こぶ
 エゴのネコアシ 2024/6/27 川村美術館(西村)
エゴのネコアシ 2024/6/27 川村美術館(西村)
 エゴノキの実 2018/7/27 長柄 (西村)
エゴノキの実 2018/7/27 長柄 (西村)
作成者:米澤 理雄 西村 安正
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。