NPO法人千葉県森林インストラクター会
種 名
漢字名
飯桐
別 名
英 名
学 名
樹木区分
落葉高木
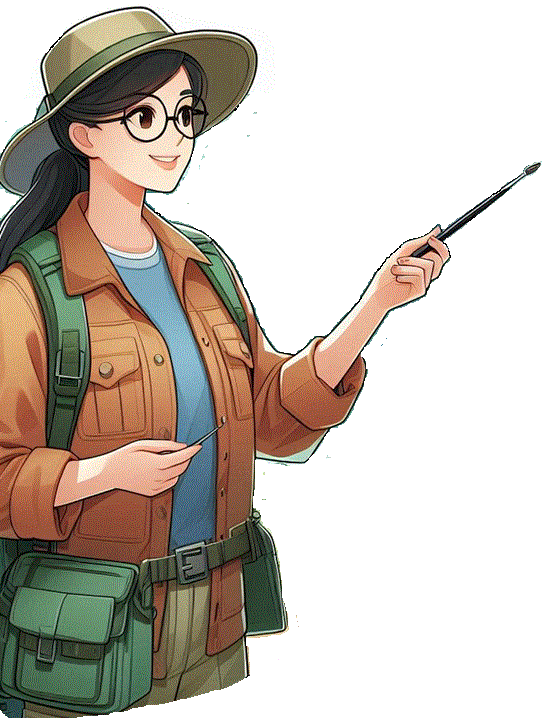
森林インストラクターの一口メモ
材がキリに似て、昔この葉で飯を包んだことによる。「キリ」は材が白くて軽い。別名は実のつき方がナンテンに似ていることによる。属名はオランダの植物学者にちなみ、種小名は果実が多いことを意味する。種を数えてみたら 24個あった。
<分布状況>
( 千葉県レッドデータブック ― )
千葉県
分布が限られているか、生育が少ない。
全国
本州~沖縄。
<生息地・生息環境>
山地や里山に点々と生える。公園、庭園、校庭。
<特 徴>
- ナンテンギリの別名のとおり、初冬、ナンテンに似た赤い実を房状につける。高さ 10~15m.の落葉高木。直立する幹から枝を車輪状に出し、独特の樹形なる。このような枝ののばし方はミズキなどの広葉樹でみられるが、イイギリは枝が太いのが特徴である。雌雄異株。学名の polycarpa は poly「多い」と carpa「果実」の意味で、多くの果実をつけることによる。
- 葉は大きな三角状の心臓形で、縁には粗い鋸歯あり互生。葉の葉脈は、つけ根から5から 7 本伸びる「掌状脈」でよく目立つ。
- 花期 4~5 月。黄色い花は、良い香りがある。雌花は花の中心に丸い子房がある。果実 10~2 月。葉は大きなハート型。赤く長い葉柄(10~20cm)の先端にイボ状の蜜腺が一対 2 個ある。葉柄の下にも蜜腺がある。
- 苦い、くさい、まずい、鳥に不人気な美しい実。ネズミモチなどの実を食べつくした後に、ヒヨドリが集まってくる。まずくすることで種子の散布時期を調節しているのかもしれない。
- 雌雄異株で、雌株には赤い実がブドウのような房にたれる。実の房の長さは 20~30cm。シロミノイイギリといって、白い実をつけるものもある。
- 試食すると、果肉は苦くて悪臭があり、とてもまずい。
- 実の中には小さな丸い種(2mm 足らず)がたくさん(数十個)入っている。落葉後もしばらく枝に残り、冬の間ヒヨドリやツグミなどの貴重な餌となる。年を越えても残っており、ヒヨドリたちは他の実より遅い 12 月頃から食べ始める。
- 枝の落ちた痕が大きな目玉模様となり非常に目立つ。葉がキリの葉に似ていて、その昔、この葉でご飯を包んだことから「飯桐」の名がある。葉には毛がなく飯がつきにくい。
- DNAの分類でヤナギ科となる以前は1属1種の樹種であった。排水がよく、風当たりが少ない山中によく生える。
- 実は熟して赤色から黒色になる。
- 冬芽はべたべたした樹脂に包まれている。葉痕は円形で大きく維管束痕は三か所で多数。側芽は頂芽より小さい。枝は皮目が多い。
<類似種・一緒に覚えたい樹木>
アカメガシワ、ミズキ、キリ、クサギ、アブラチャン、キササゲ
<見分け方>
アカメガシワとの不分裂の葉とよく似ているが、はっきりと鋸歯があり、蜜腺の形も異なる。
<利 用>
- ナンテンでつくる「南天箸」は食あたりなどの諸毒を消し、長寿を祈願するとして好まれますが、市販されているほとんどのものがイイギリ材である。イイギリは赤い実が垂れ下がり、ナンテンに似るためナンテンギリとも呼ばれ代用される。箱材や下駄材などキリ材の代用。

作成者:内藤 公雄
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。