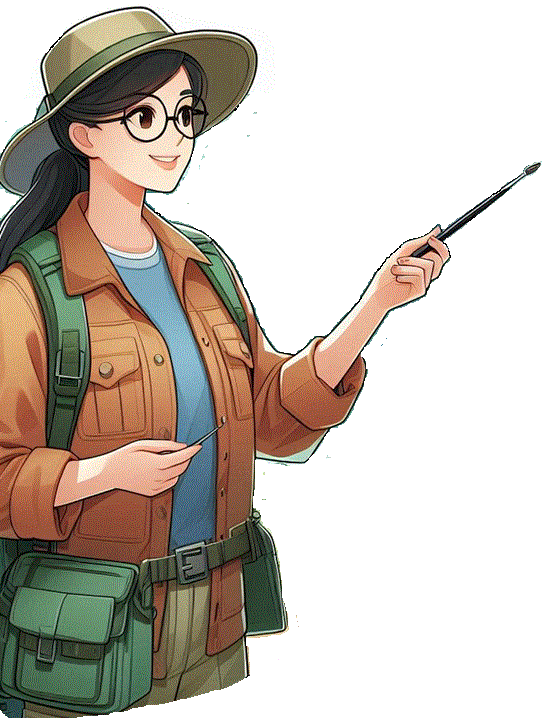ゴサイバ(五菜葉)、サイモリバ(菜盛葉)、メシモリナ(飯盛菜)
アカメガシワの新芽にセロテープを貼り、セロテープをはがしてみると、毛であることがわかり、面白い。「紅色の軟毛におおわれている新芽を摘み取り、熱湯でゆで、水にさらして、ゴマダレなどで和える。伸びた若葉は天ぷらにする。」とあるが食べたことはない。
千葉県
県内に広く分布し、生育が普通にみられる。
全国
本州~沖縄。
伐採地、空き地などに、再生した林として先駆的に生えるパイ ニア・プランツの一つ。山野の日あたりの良い場所に、ごく普通に生える。
- 幹は斜めに伸びて逆三角形の樹形になる。樹高5~15mになる落葉樹。花期は6~7月。
- 幼木の樹皮は灰褐色で、縦に筋模様が入る。成長とともに、縦に細長い網目状の模様となる。
- 浅く3つに裂ける葉の形と、赤くて長い葉柄が特徴。名の由来である赤い若葉が枝先に目立つことや、葉の基部にある蜜腺が良い見分けのポイントになる。葉の基部にある一対の蜜腺から蜜を出し続けているため、アリがやってきて舐めている。雌雄異株で雄花は香りが強い。
- 先につく芽(若葉)が赤いので赤芽柏の名がある。新芽の赤さは名の由来でもあるが、細胞内の色素ではなく、表面に生えている毛の色である。爪で少し削ってみると緑色が現れる。
- シワとは別の仲間だが、 シワと同様に大きな葉は食べ物をのせる器として使われてきた。葉は通常、3つに浅く切れ込むが、木が大きくなると、切れ込みがない葉が増える。明るいところでしか育たないので、暗い林の中では見かけない。道路端や造成斜面、あるいは庭の隅などにも勝手に生えてくる雑草のような木で、このように日当たりのよい場所に真っ先に侵入する木を先駆性樹木(パイニアツリー)と呼ぶ。先駆性樹木は、成長が非常に速く、やせ地でも良く育ち、比較的短命という性質がある。芽吹く種に巧妙な仕掛けが施されていて、25℃の温度で数日、32~40℃の温度で数時間、最後に 20℃以上の温度にしばらくさらされるといった三段階の条件が必ず必要である。本種と葉が似るウリノ は、暗い林内に生える木で、生育環境が対照的である。
- アカメガシワのタネは土の中で 20 年以上も眠り続けるといわれ、林の木が切られたりして明るくなると、眠っていたタネが芽を出す。このようなタネのことを埋土種子という。
- 頂芽は大きく、葉の形がわかる。側芽は小さい。葉痕はほぼ円形。維管束痕は多数が輪状やU字形に並ぶ。
- 枯れたアカメガシワには クラゲの仲間が好んで取りつく。ヒラタケの栽培にほだ木として使われ、成長の速さからも効率の良い経営ができると注目される樹木。
イイギリ
葉の裂け目は成長とともになくなり、樹高が 4mを超えるような木では、大半が不分裂葉になる。不分裂葉はイイギリに似ているが、イイギリは鋸歯があり、蜜腺の形も異なる。
- 樹皮は薬用にされ、中国では野梧桐と称し、樹皮を消炎鎮痛薬として胃酸過多や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胆石などに利用されている。日本でも整腸アニイン薬の生薬として、第十三改正日本薬局方にアカメガシワの樹皮が加えられ、樹皮のエキス製剤が市販されている。
- 民間薬として古くから、葉や樹皮を夏に採取し、「切らずに治す腫れ物薬」として汗疹や皮膚病、神経痛に用いた。樹皮には苦味物質のベルゲニン、葉にはゲラニインなどが含まれており、ベルゲニンには胃液分泌抑制作用と抗腫用作用が認められ、ルチンは胆汁成分を促進するが、冬に採取した樹皮は時にアレルギー症状を起こすこともあるため、取扱いが大変難しい薬木。
作成者:内藤
本サイトの記事・画像等の無断転載は禁じます。